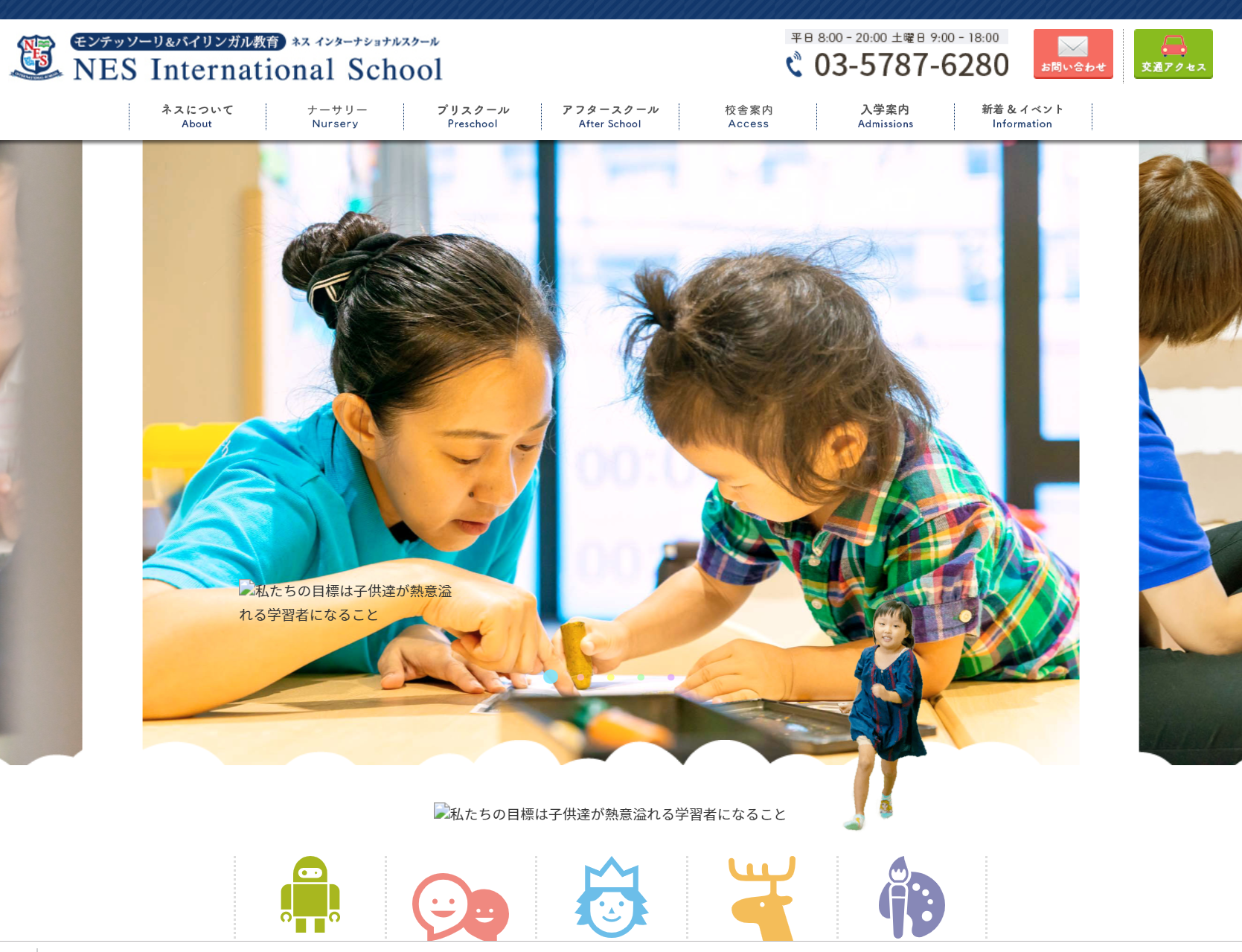認可外保育園も無償化に保育料と補助金を徹底解説
◯ 導入
幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が2018年の5月10日に可決・成立し、2019年10月からの実施が決定しました。
無償化というと、
- 認可外保育園も対象なのか
- 教育費が全くかからないのか
- 条件や対象の世帯が決まっているのか
など疑問に思うことはたくさんありますよね。
私も無償化と聞いた時は「完全無償化なのかな?そしたらありがたい政策だな」と思いました。
実際に政策について見てみると、「完全無償化」とはいかないようですが、認可外幼稚園も対象となるとのことです。
そこでこの記事では、無償化の制度についての詳細や無償化を賢く利用して認可外保育園に通うメリットなどを、認可外保育園に焦点を当てて、紹介していきます。
これから子どもを保育園に通わせようとしているパパママは、ぜひチェックしてみて下さいね。
認可外保育園とは?

まずは認可外保育園がどういうものなのかよくわからないという方もいらっしゃると思うので、どうゆうものなのかを解説しますね。
そもそも認可外保育園とは何か?
認可外保育園とは児童福祉法上の保育所に該当しているが、認可保育園とは異なり国からの認可を受けていない保育施設のことです。
それぞれの認可外保育でも目的や特徴、保育内容は異なります。
理想の教育方針を貫くために認可外であり続ける園もあるなど、国の基準に縛られることなく運営を続ける園もあるほど。
そして認可外保育園は直接、園に入園を申し込む制度なので、入園先を選べるのも認可外の特徴です。
認可保育との違い
認可保育と認可外保育とは簡潔にお伝えすると、国が定めた基準を満たして許可を得ている保育園と、それ以外の保育園という違いがあります。
認可保育園は、法律上では「保育所」という名称です。
保護者が働いているなどの理由で、十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象とした、預かり保育をする厚生労働省が管轄している「児童福祉施設」のことを指します。
主な違いは以下の通りです。
|
認可保育園 |
認可外保育園 |
| 保育施設の分類 |
保育所 |
ベビーホテル・企業内保育所など |
| 設置基準の違い |
厚生労働省が定めた一定の基準。 |
厚生労働省の定めた一定の基準を満たしていない。
※決して環境が悪いわけではなく、アットホームな環境や駅チカなど保護者のニーズに合わせた施設が多い。 |
| 保育料や運営費の違い |
【保育費】
家庭の水準によって異なる
【運営費】
国や自治体からの補助金あり |
【保育費】
園によって異なる
【運営費】
基本的に国や自治体からの補助金なし |
| 環境や規模の違い |
預かる子どもの年齢と定員に対して敷地面積や遊具施設などの設備基準が決められている。
広い敷地面積が必要なため、駅から遠いなることも多い。 |
認可保育園に入れなかった子どもを預かるため、駅から近い施設が多く、施設面積が狭い園もある。
逆に運営方針によっては認可以上の面積や施設を備えている園もある。 |
| 運営方針の違い |
【公立】
各自治体で定められた保育計画に沿って公立園の間で差が無いように運営
【私立】
各運営母体が独自に定め、それぞれの方針に沿ったカリキュラムを運営 |
運営する法人によって保育理念や方針が大きく異なるので、個性が豊か。
認可保育園にはない独自の教育を行う園も多い。 |
認可外保育園は、認可保育園では満たせない、保護者のニーズを満たすための受け皿とも言えます。
認可を受けていないから危ないとは限らない
国からの認可を受けていないからと言って、決して環境が整っていない訳ではありません。
認可園に比べて、認可外は制約が少なく、保護者のニーズに柔軟に対応することができるのです。
たとえば、認可園は許可を得るために必要な敷地面積が広いため、駅から離れた立地に建てられていることが多いです。
もし、入園した保育園が駅とは異なる方向にあると、働くパパママは通勤途中に子どもを預けて駅に向かうことが難しいです。
子どもを預けるために早く家を出て遠回りしないといけなくなります。
ただでさえ慌ただしい朝の時間が更にバタバタしてしまいますよね。
このようなニーズに応えるため、国からの認可を得るのではなく、わざと敷地面積を小さくして駅から近い立地に園を構える法人もあります。
こうした方針は保護者のニーズに柔軟に応えられていますよね。
他にもカリキュラムの自由度を高く、英語教育など独自の活動に多く時間をさいている園もあり、それぞれの園で特徴があるのが認可外保育園の魅力です。
認可外保育園メリット

認可外保育園について分かったところで、認可外保育園に通うことのメリットを6つ紹介していきます。
- 英語や知育、教育に力を入れている園も多い
- 保育時間、保育日数の柔軟な対応
- 在住・在勤・在学の地域にかかわらず入園可能
- 保育理由を問われない
- 所得によっては認可より安上がり
それではそれぞれ見ていきましょう。
1.英語や知育、教育に力を入れている園も多い
幼児教室やインターナショナルスクールが運営母体にあると、保育時間に「お勉強」をさせてくれる園もあります。
具体的にはモンテッソーリ教育やシュタイナー教育など、世界の教育法を方針としている園には教育熱心な保護者が集まっています。
2.保育時間、保育日数の柔軟な対応
認可外保育園は保護者のニーズに合わせて、預ける曜日や時間帯を決めることができます。
週3から預けることができたり、時間帯も早朝・夜間・休日などフレキシブルに対応している園もあります。
シフト勤務やパートタイムで働いている保護者の場合、認可保育園では十分に対応してもらえないこともあるので、小学校入学まで認可外保育園に預けているパパママもいるほどです。
3.在住・在勤・在学の地域にかかわらず入園可能
認可保育園の場合は在住、在勤、在学の自治体に申請する必要がありますが、認可外保育園の場合、これらの地域は関係なく入園することができます。
そのため、区境に住んでいる家庭は隣の認可外保育園に通わせることも可能です。
4.保育理由を問われない
認可保育園とは違い、認可外保育園は直接園と契約をします。
園に空きがあれば、就労証明書が無くても(母親が働いていなくても)入園することができます。
そのため、これから働く予定で休職中であっても入園の可能性は広がるのがメリットです。
5.所得によっては認可保育園より安上がり
認可保育園は世帯の収入によって保育料が異なるので、世帯での合計収入が多ければその分、保育料も上がってしまいます。
一方で認可外保育園は、保育料が園の定めた一定の料金です。
そのため認可外保育園であっても、世帯の所得次第では認可保育園よりも安い場合があります。
6.国の要件を満たし、立ち入り検査を受けている
国の認可を受けていないと聞くと、安全面や環境面でしっかりしているのかなと心配になる保護者の方は多いでしょう。
実は認可外保育園も「認可外保育施設指導監督基準」という、国からの許可基準を満たすことが必要です。
すべての認可外保育園が指導監督の対象となっていて、定期的に立ち入り調査を実施しています。
届出対象施設の設置者には「サービス内容の提示」、「契約内容の書面交付」などが義務付けられているので、安心して子どもを預けられますよ。
認可外保育園が2019年10月から無償化に

冒頭でお伝えした通り、2019年の10月から幼児保育の無償化が全面的に実施されます。
これは認可園だけではなく、認可外園も対象です。
10月に実施と言いつつも、実は5歳児の子どもは既に2019年の4月から無償化が実施されているなど、細かい政策について把握していない方も多いと思うので、詳しく解説していきます。
・これまで段階的に行われていた無償化が、全世帯で無償化に
今回の国の決定に先立ち、以下の内容で既に保育料を無償化している自治体もあります。
| 段階的に行われている取組の内容 |
「平成29年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組」として、年収約360万円未満相当の世帯について、従来の政策であった「多子軽減における年齢の上限」を廃止。
そして同時に年収360万円未満相当のひとり親世帯などについては、負担軽減措置を拡大し、第1子から無償化する取組。 |
この取組が段階的に行われていましたが、2019年10月からは全世帯での無償化を実施することになったのです。
・対象年齢ごとに、どこまで無償化されるのか
では実際に対象年齢ごとに、どこまで無償化の対象になるのか気になりますよね。
この無償化の取組みで対象になるのは以下の子どもの環境と保育施設になります。
取組み内容は3~5歳と0~2歳までの2つにわかれます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
【3~5歳】
| 子供の環境 |
対象の保育施設 |
「保育の必要性の認定」を受けた家庭の子ども
(共働き・シングルで働いているなど) |
単独利用が対象
|
単独利用が対象
|
単独もしくは複数利用も対象
- 認可外保育園
※届出をしている施設が対象
- ベビーシッターなど
|
複数利用の場合
|
上記の認定を受けていない家庭の子ども
(専業主婦など) |
単独利用が対象
|
単独利用が対象
|
複数利用の場合
|
【0~2歳】
| 子供の環境 |
対象の保育施設 |
住民税非課税世帯
(以下の場合を指します。)
- 生活保護を受けている家庭
- 世帯主が未成年、障害者、片親で前年度の合計所得が125万円以下
(収入が204万4000円未満)
- 前年度の合計所得が35万×世帯人員数+21万円以下
|
単独利用が対象
|
単独もしくは複数利用も対象
|
上記で挙げている、それぞれの施設については以下で確認いただけます。
| それぞれの施設について |
| 保育所 |
児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」のこと=認可保育園 |
| 幼稚園 |
3歳~小学校入学までに通うことのできる「教育施設」のこと |
| 幼稚園の預かり保育 |
幼稚園の教育時間外(前後の時間帯や土日、長期休業中)に幼稚園に預けること |
| 認定こども園 |
「児童福祉施設」と「教育施設」の特徴をあわせもつ複合型保育施設のこと |
| 認可外保育園 |
国からの認可を受けてないが、「児童福祉法第59条の2」による届出がされている保育施設のこと |
| ベビーシッター |
保育施設に通わずに、母親の代わりに個別で保育をすること |
| 障害児通園施設 |
児童福祉法によって法的に規定された知的障害児と肢体不自由児が通う施設のこと |
上記の表で解説している通り、どの保育施設に通うか、また子どもの環境(共働きなのか専業主婦なのか)によって補助金の金額が異なってきます。
認可園に通うよりも、認可外を複数利用している方が補助金が高い、もしくは同じ金額をもらえる場合もあります。
対象になる認可外保育園について
上記の表の通り、認可外保育園は無償化の対象になりますが、適応されるためには施設側と利用者側にそれぞれ条件があります。
【施設側】
- 認可外保育施設
- ベビーホテル
- ベビーシッター
- 子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
など、これらのサービスで無償化を適応する場合は、各施設や事業主が都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準である「児童福祉法第59条の2」を満たす必要があります。
現在は経過措置として、指導監督基準を満たしていなくても、届出自体がされていれば5年間の猶予期間を設けています。
5年以内に指導監督基準を満たす意志のある施設には、無償化が適応されるという措置です。
ただし、猶予期間である5年経過しても指導監督基準を満たしていない場合は、無償化の対象外施設になるので注意が必要です。
【利用者側】
「保育の必要性の認定」が必要。
5年以内に指導監督基準を満たす意志のある施設には、無償化が適応されるという措置です。
対象の3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児は「保育の必要性の認定」を受けた家庭の子どもが無償化の対象として、利用料に補助が受けられます。
「保育の必要性の認定」とは、平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」という制度に基づき、保護者の申請を受けて、就労証明書や診断書などの客観的な基準により、各自治体が保育の必要があるか判断するものです。
無償化に伴い、新たな「保育の必要瀬の認定」を定めているので、現行の認定か新たな認定のどちらかで認定を受けることができれば無償化の対象になります。
・保育料無償化(幼児教育無償化)の案内HPが公開
2019年10月の実施に先立てて、内閣府が幼児教育・保育の無償化の案内のページを立ち上げました。
このページでは、実際に無償化についてシミュレーションすることができます。
あなたの家庭でどのような支援が受けられるのか具体的に確認することができるので、気になる方はチェックしてみて下さいね。
認可外保育園に通わせて上手く利用したい補助金制度

続いて認可外保育園に通わせる場合、どのくらい補助金が受け取れるのか見ていきましょう
・認可外保育園で利用可能な補助金について
前提として、認可保育園に通う場合は保育料がすべて無償です。
認可外保育園では3~5歳児を園に預けると、月に3.7万円を上限に補助金が貰えます。
また、住民制非課税世帯の0~2歳児であれば月に4.2万円が上限の補助金として受け取ることができます。
さらに、上限額内であれば、ベビーシッターなどの複数のサービスを併用することも可能なのです。
- 3~5歳児:月に3.7万円の補助金(認可外保育園の場合)
- 住民制非課税世帯の0~2歳児:月に4.2万円の補助金
- 上限金額内なら併用可能
少しずつではありますが、働く親が子供を保育園に預けやすい仕組みが作られていることは嬉しいですね。
認可外保育園の補助金は手続きが必要なのか?
パパママを助ける補助金制度ですが、手続きの方法も気になりますよね。
認可外保育園の補助金を受け取るためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けるためには、各自治体の窓口で申請をし、家庭の状況に応じての確認が必要になるので、お住まいの自治体の窓口で確認をしてみましょう!
認可外保育園で補助金制度が適応した場合の実際の保育料は?

認可外保育園の無償化の詳細が分かってきたところで、実際にどこまでの範囲が無償化になるのか見ていきましょう。
認可外保育園で無償化になる費用の範囲とは
認可外保育園の場合、最大で付き3.7万円の補助金を受け取ることができます。
例えば、保育園の費用が月5万円だとすると、3.7万円は自治体方直接保育園に支払われるので、残りの1.3万円は家庭で負担することになります
ここで指している保育園の費用というのは、純粋な保育料となり、食事や送迎費などは含まれません。
対象外となる詳しい費用は次項で解説しているのでご確認ください。
認可外保育園で補助金の対象外となる費用とは
保育園によって、かかる費用が異なるので、以下は一例になります。
参考までにご確認くださいね。
- 通園送迎費(スクールバスなど)
- 食材費(給食など)
- 行事費(遠足など)
- 制服代や体操着の費用
などを家庭で負担することになります。
また注意が必要なのが、「対象になる認可外保育園について」の項目でもお伝えした通り、国が定める指導監督基準に届出を出していない認可外保育施設や事業は保育無償化の対象外となります。
5年間の猶予期間に指導監督基準を満たすことができなかった施設に対しては、無償化の対象から外れることになります。
現在の猶予期間は5年と定められていますが、期間が短縮される可能性もあるでしょう。
5年あるからと安心するのではなく、届出を出し基準を満たしている認可外保育園を選ぶようにするのがおすすめです。
認可外保育園が問題視される理由

認可外保育園について紹介してきましたが、やはり認可されていないと安全面で不安な方もいるでしょう。
認可外保育園が問題視されている理由は、主に保育の質や保育士の人数などが挙げられます。
自治体に届出をしている認可外保育園は、国の指導監督基準を満たす必要があり、届出をしている施設すべてへ立ち入り調査を原則1年に1回、実施しています。
しかし、実際に立ち入り調査されている施設の割合は70%ほどです。
年々認可外の施設が増えているため、100%すべての施設を調査するのは難しいようにも思えます。
とはいえ、子どもの安全確保が第一になるので、働くパパママが安心できるように、すぐにでも対応すべき問題ともいえます。
もう1つの問題視されている理由である、保育士の不足です。
保育士は資格を持っていないと保育施設で働くことができません。
そして、お給料もあまりよくないので、働きたいと思う人が少ないのが事実です。
この問題は認可外だけに関わる問題ではなく幼稚教育全体に関わる問題でもあるため、保育士の賃金を上げる政策が実施されています。
問題視されている理由を見てきましたが、一方で認可外保育園の中には認可園以上に基準を気にしていたり、保育に力を入れている園もたくさんあります。
認可外保育園と言っても、教育方針や保育環境、安全面などはほんとうにさまざまです。
悪いイメージを持って見学に行くと、思ったより良かったという意見もあるほど。
良い認可外保育園を見分けるためにも、手間はかかってしまいますが数多くの保育施設を見学しましょう!
かしこく認可外保育園を活用するには?

認可外保育園を見学する際にどの点を注意して見るべきかわからないと、賢く活用できないですよね。
ということで、かしこく認可外保育園を活用するために、見学時に確認しておくべきことを紹介しますね。
抑えておくべきポイントは以下の6つです。
| 1 |
職員の人数と保育士の有資格者の割合 |
認可保育園は保育士が100%でないと保育を行えませんが、認可外保育園が有資格者は100%である必要はありません。
有資格者が50%以上の施設もあります。
保育士の割合を確認しておきましょう。 |
| 2 |
子どもの過ごしている環境 |
ワンフロア―でもしっかりと区画されていれば問題ありませんが、そうでないとケガなどのリスクが上がるので注意が必要です。
園児の発達レベルによって、区画されているか確認しましょう。 |
| 3 |
安全面が考慮されているか |
認可外保育園でもしっかりしているところであれば、カメラや玄関のオートロックなど、事故や防犯対策をしっかりしています。
また、子どもから目を離していないかなどの保育士の対応もしっかりチェックしておきましょう。 |
| 4 |
認可保育園に負けない独自性があるか |
認可校以上の魅力やアピールポイントがあるか確認しましょう。
など、他にはない独自性があるかは大きなポイントです。
|
| 5 |
入所までの流れを確認 |
入所までの手続きは施設によって方法が異なるので、流れを確認することも大切です。
保育料を早く支払うように言ってくる場合は気を付けましょう!
経営がひっ迫している可能性もあります。 |
| 6 |
すべての質問にしっかり答えてくれるか |
個人情報に関しては、守秘義務があるので回答できませんが、それ以外の以下のような内容にしっかり答えてくれるか確認しましょう。
- 保育内容
- 子どもたちの様子
- 職員の配置状況
- 保育時間中の遊びや、おもちゃ
- 給食の内容
- 安全面の対策
とくに安全面の対策に対してしっかり答えられている施設はしっかり対策を実施していると言えます。
|
この6つの内容は実際に施設を見学や話を聞いてみないとわからないことです。
実際に施設を見てみることは大切なので、手間が掛かってしまいますが、必ず足を運ぶようにしましょう!
ネスインターナショナルで教育ポリシーや英語保育などの高水準の教育を
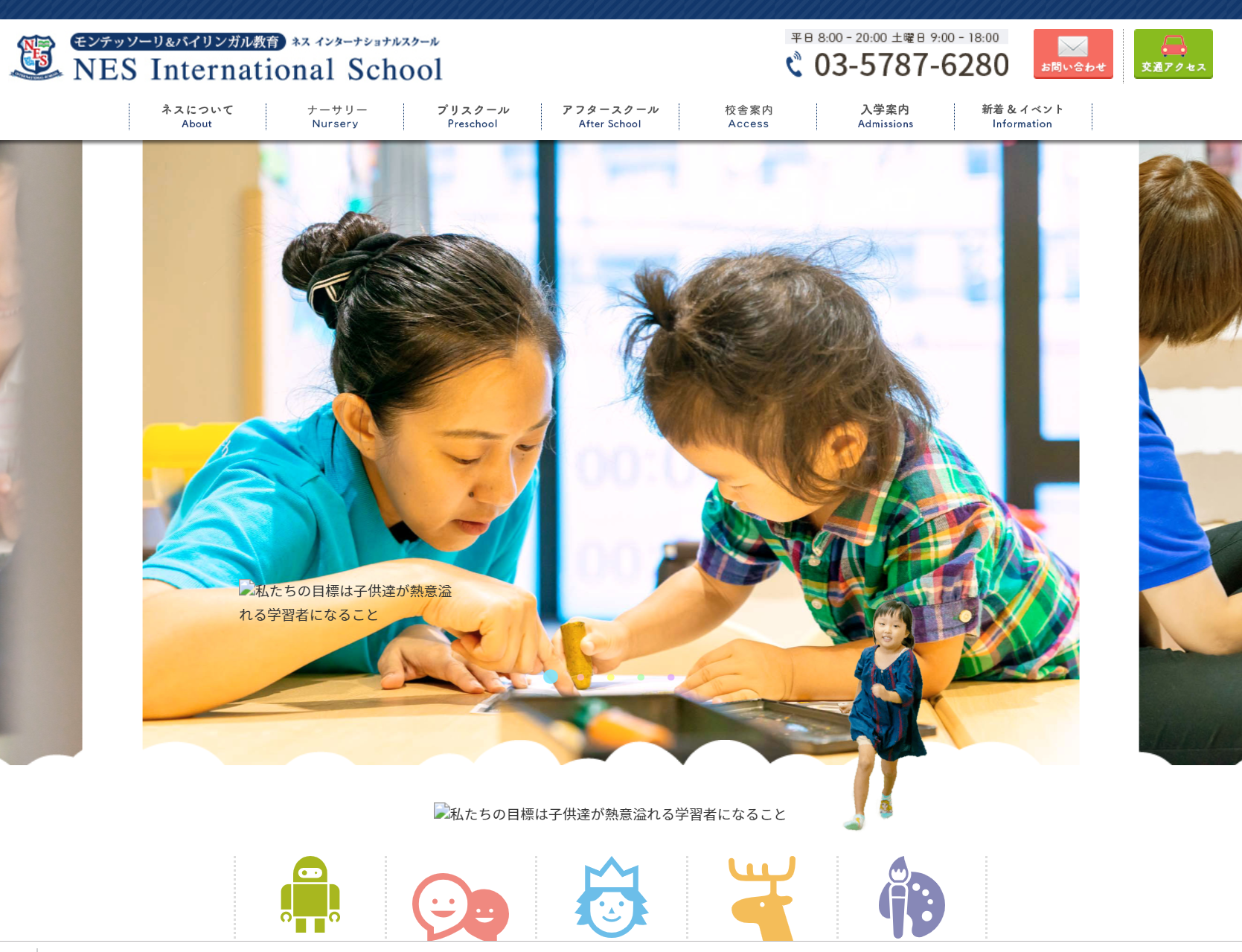
あなたの家庭で大切にしたい教育は決まっていますか?
まずは家庭の教育方針を再確認してみましょう。
現在子育てをしているパパママが気になる教育の1つは英語ではないでしょうか?
これからの日本は更にグローバル化が必要になってきます。
そんな社会で活躍できる日本人になるために、英語教育は必須ですよね。
私たち、ネス インターナショナルでは、英語教育に加えてグローバル社会に優秀で健全なリーダーを育てるための幼稚教育を行っています。
母国の文化を主軸に、異なる言語・文化・価値を十分に理解し、世界的な競争が進むグローバル社会において、コミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力を培い、次世代を視野に優秀で健全なリーダーを育てます。
これらの教育はモンテッソーリ教育に基づき組み込まれた理念です。
モンテッソーリ教育について詳しく知りたい方は「モンテッソーリ教育とは」で内容をチェックしてみて下さいね。
私たちの具体的な目標は、プリスクールでは3歳までにアルファベットを読めるように、アフタースクールでは小学校3年生までに英検3級に合格するように、バイリンガルキッズの育成を行うことです。
施設の名称は「ネス インターナショナル」ですが、認可外保育園として届出をし、国の指導監督基準を満たしています。
幼稚教育の無償化の対象になるので、安心してお子様を預けていただけます。
ネス インターナショナルは全部で3つのスクールがあります。
- ナーサリー
- プリスクール
- アフタースクール
| スクール |
年齢 |
時間 |
校舎 |
| ナーサリー |
0~2歳 |
平日・土曜日
7:30~20:30 |
横浜たまプラーザ |
| プリスクール |
0~5歳 |
平日
8:00~20:00
土曜日
9:00~18:00 |
世田谷駒沢校
※幼児教育無償化対象 |
| アフタースクール |
3~10歳 |
月~金
14:00~20:00
土曜日
9:00~18:00 |
世田谷駒沢校
横浜たまプラーザ
新潟駅南校
|
【ナーサリー】
モンテッソーリ教育を採用。
「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てる」ことを目的としています。
子どもの発達段階に適した環境を整え、知的好奇心を自発的に育みます。
モンテッソーリの教室は社会性・知的協調真を促すために異年齢混合のクラスです。
このクラスの中で、年下の子は年上の子の活動を見て学び、年上の子は年下の子の世話をして、子どもたちはお互いから学びあいます。
【プリスクール】
アメリカの幼稚教育カリキュラムである、ファーストラーニングを導入。
- アメリカン・ラーニングシステム
- 子どもの発達段階に応じたプログラム
- 子どもの教に分野に基づく環境設定
- 専門のティーチャーによる学習サポート
- 幼稚教育の情報提供と育児カウンセリング
アメリカの幼稚教育カリキュラムをベースにした多彩なプログラムを通して、創造性や考える力を身に付け、子どもたちの積極的な学習姿勢を育みます。
【アフタースクール】
グローバル基準のカリキュラムで学ぶ英語総合学習「アフタースクールラーニング」を導入。
- アメリカの幼稚教育メソッドの提供
- プログラミング学習
- リーダーシップスキルの育成
- 春・夏の海外研修(親子留学あり)
英語だけでなく、主体性・積極性・チャレンジ精神・協調性・柔軟性・責任感・使命感・異文化に対する理解と言った総合的な能力をつけることをゴールに、未来のグローバル人材を育てます。
まとめ:認可外保育園で無償化の補助金を賢く利用

認可外保育園の無償化について詳しく解説してきましたので最後におさらいです。
認可外の保育園は全額補助ではありませんが、上手に利用することで、認可保育園と同じだけの保証金を受け取ることができます。
認可外保育園は認可保育園に比べて、質の振れ幅が大きいのも事実です。
認可外の保育園を利用する時は、必ず事前に見学に行きその施設の運営方針やルール、施設の安全性などを確認しましょう!
ネスインターナショナルは高い質を保ちながら、英語教育に加えてグローバルに活躍できるための教育を実施しています。
お問い合わせいただけましたら、詳細をご案内させていただきますのでいつでもご連絡くださいね。